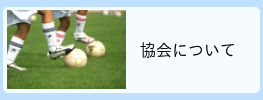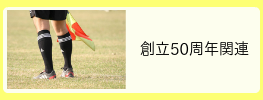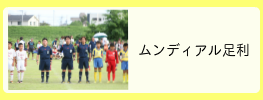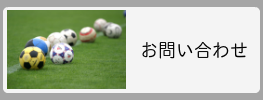2025年度
令和7年度専門部・委員会活動方針
チームに属していない子どもたちや、サッカーとは縁の遠かったお父さんお母さんと親子で体験するサッカー教室や、チーム所属の家族の方には参加型のイベントに積極的に参加していただきサッカーの楽しさを試合とは違う目線、角度で知っていただく企画作りに取り組み、新たなサッカー好きを見つけ、作ることに働き続けます。
また、幼年部の年代では、まず「楽しく」をモットーと位置付け、サッカーの「楽しい」とは何か、勝利にとらわれず「おはようございます、ありがとうございました」と、挨拶から感謝までフェスや大会などを通じて子どもたち選手がリスペクトを感じ考える。そして活躍する場所作りに我々は専念していきます。
「すべての人にサッカーを」。老若男女みんなでサッカーを楽しみ、未来に向けて活動することで自然とサッカー人口が増えてくれると期待し、その為にこれまでの経験を見直し変化を求め協会組織で新しいことへの挑戦に積極的に取り組んで「動く」所存です。
<少年部> 中 島 弘 義
少子化・サッカー人口減少が進行する中、子どもたちがサッカーを楽しめる環境を整備することは、子どもたちの健全な成長と未来にとって重要です。しかし、指導者・審判の不足やチーム数の減少など、さまざまな課題が存在します。
このような状況に対応するため、地域の公園を活用して、子どもたちが自由にサッカーを楽しめる場を提供する取り組みが注目されています。ある地域では、特定の時間帯に公園でボール遊びを許可し、大学生ボランティアが子どもたちと一緒に遊ぶ「プレーリーダー」制度を導入しています。これにより、子どもたちは安全にサッカーを楽しむことができ、地域コミュニティの活性化にもつながっています。
また、経済的な理由や家庭環境の問題でサッカーを諦めざるを得ない子どもたちを支援する活動も重要です。あるNPO法人は、「子どもサッカー新学期応援事業」を通じて、サッカー用具の提供や奨励金の給付、プロサッカー選手との交流機会を提供しています。この取り組みは、サッカーをしたくてもできない子どもたちにとって大きな支えとなっています。
足利市でもこれらの取り組みを参考にし、子どもたちがサッカーを楽しめる環境を整備し、少子化時代においても子どもたちの未来を明るく照らす取り組みを模索していきたいと思います。
<中学部> 小 堀 賢 司
今年度、足利の中学生がサッカーに取り組む状況は大きく変わろうとしています。休日の部活動の地域移行について、サッカー部と野球部が先行モデルとなり、クラブチーム化がすすめられることとなります。サッカー部においては、すでに毛野中と協和中が母体となる東地区のクラブチームが県協会に認証されており、今後は他地区でも同様の動きをとることとなります。チーム数の減少や指導者に関する問題など、課題も数多くあります。しかし、今までサッカー部が無かった中学校の生徒がサッカーをプレーしやすくなる、というメリットもあります。足利市の中学生が市内でより高い競技性を求めてサッカーをしようとすると、ユナイテッドFCというジュニアユ-スチームでの活動を選択することもできました。しかし、そこまで競技性を追求しないでサッカーをやろうとすると、通学している学校にサッカー部がないと希望を叶えることができませんでした。このことから、サッカー人口の減少に歯止めがきくことも期待できます。指導者については、ジュニア時代に自分の子どもを指導されていた方が中学年代でも指導を続けてくださることが理想です。現在も「外部指導員」という形で携わってくださる方もいますが、基本的には休日の指導は学校外の方が主導になる見通しなので、子どもたちの特性をよく知る方が指導してくださることは大変心強いことです。
いずれにしても、中学部だけで進行できる問題ではないことに違いはありません。チーム間のつながりとともに、協会の協力を得ながら少年部や高校部との連携をより一層強くすることで選手の不安を軽減させ、一人でも多くの選手がサッカーを続けられる環境をつくっていきたいと思います。
<高校部> 内 田 才 也
高校部は、さらなる組織の活発化および世代間の交流が積極化による「サッカーファミリー」が拡大する活動を積極的に行動に移せればと考えています。
各校とも、長年サッカーの指導に携わってきた指導者や、ライセンス取得者が揃っています。サッカーにおける技術向上の指導はもちろんの事、サッカーを通して人間力を向上させ、仲間を大切にする精神を涵養し、次のステージで活躍できる人材の育成を目指していきます。また、「サッカーファミリー」の中核としての自覚をもった行動をとれるように、選手を導いていきます。
さらに世代の垣根を超えた交流、例えば中学生との練習会、試合の実施などを通し、人間関係の構築を図り、選手はもちろん指導者同士の繋がりを大切にしていきたいとも考えています。
足利市内の高校でサッカーをしたいという環境と、足利市内の高校が市民の方々に応援してもらえるようなチーム、サッカー文化が根付くよう、そして栃木県を代表するチームを足利市の高校から出せるように、組織的に活動していきます。
<社会人部> 齋 藤 琢 哉
本年度は市民リーグからシニアリーグへ移行するチーム、県リーグに挑戦するチームがあり市民リーグから退くチームがある中、新規2チームが参戦していただくことになりました。
県リーグも退くチームもあり、激動の一年となります。社会人もサッカー離れは深刻な問題です。人と環境、全てが整うことはこのご時世厳しい状況です。
そんな中でも各チームは新たな若手や新人を受け入れる環境を今後も残すためにチーム存続を常に考えることが必要です。少しでも社会人サッカーに興味を持っていただけるよう各チーム様々な形で発信していければと思います。
<シニア部> 長 栄 一
本年度はおかげさまで昨年より2チーム増で登録14チームでの活動となります。
基本は以前と同様チーム間の親睦と「楽しいサッカー」をモットーに行います。
昨年度はケガが1件発生しました、本年度は絶対ケガをしないケガさせない事を第一に各チームに周知させ運営したいと思います。シニアリーグの観戦にあしスタに来場する人も少しは見受けられるようになりました。今年もより一層各人が誘いあって選手以外の方にも多数観戦いただき中高年が楽しそうにサッカーをしている姿を見ていただきたいと思います。
<女子部> 板 橋 稔
サッカー競技人口の減少が問題となっている昨今、女子サッカーにおいては、ますますその状況が顕著になっています。まずはサッカーに興味を持ち、女子サッカーを始めるきっかけとなる事業展開が求められていることから、前年度に手応えがあった「女の子のためのサッカー教室」をさらに充実させながら、本来サッカーが持つ楽しさ、魅力を広く発信していきたいと思います。
また、新たな裾野の確保と同じく重要なのが、各年代の女子選手たちをきちんと次のカテゴリーへ橋渡ししていくことです。ようやく始めたサッカーを次の年代でも続けられるよう、今ある女子サッカー環境の維持、そしてさらなる充実を図っていくことが大切です。
いずれにしても、女子サッカーを通じて得られる様々な感動とともに、楽しく、そして少しでも長く、地元でサッカーが続けられる環境を提供し続けられるよう、引き続き女子サッカーの普及啓発に努めてまいります。
<普及委員会> 漆 畑 良
今年度の普及委員会も昨年同様「普及」と「育成」を考えながら、事業の発展と改革を進めていきたいと思います。
『ひとりでも多くのサッカーファミリーを増やす』を念頭に置き、土台作り(幼児・小学生年代)を中心に活動していきたいと考えています。
巡回サッカー教室・足利市サッカー教室などを通してひとりでも多くのこどもたちに『サッカー(身体を動かすこと)の楽しさ』を伝え、サッカーを始めてみたいというこどもたちの背中を後押しできればなと思います。同時に巡回施設の先生方にも指導方法などの共有をしていければと考えています。
今年度は昨年度より多く、そして新規施設での巡回サッカー教室が実施できるように頑張ります!!
その為には各専門部、委員会、そしてサッカーに携わる全ての皆様と繋がりを密にし、ご理解ご協力を頂きながら普及活動に取り組み、サッカーの街「足利」を目指していきたいと思います!
<審判委員会> 鈴 木 康 裕
昨年度は、男子代表がパリ五輪にて決勝トーナメント進出、女子代表はアメリカ代表に13年ぶりに勝利しました。一方で、審判のことに目線を向けると、競技規則の改正により、ハンドに関する内容が一部改正されました。毎年、競技規則が少しずつ変わっていくため、審判員の勉強も必要だと感じています。
スポーツが多様化する昨今、サッカーへの人気は変わることなく高いです。そのサッカーの魅力を発信するために、熱い試合、感動的な試合を選手たちと審判で作り上げていくことができれば、サッカーへの人気もさらに高くなると思います。そのために、審判委員会では、より多くの方に審判に興味をもっていただき、審判の資格取得を目指せるような活動を考えています。さらに、審判の技術向上、上級の審判員へと挑戦できるような環境の整備を、審判インストラクターの方々のご協力をいただきながら取り組んでいきたいです。
<技術委員会> 永 井 健 太
今年度も、昨年開催し好評であった栃木シティFCと共同の事業を開催したいと思います。トップチームの公開練習にプラスして指導者講習会など検討していきます。Jリーグチームの練習を見ること、S級ライセンスの監督やコーチの指導内容を聞くことはあらゆる年代の方にいい影響があると思います。
少年部や中学部とも相談させてもらいながら企画していきたいと思います。